リフォーム費用が大幅アップ?2025年建築基準法改正の影響と賢いリフォーム術

「2025年以降、リフォーム費用が上がるって本当?」
まもなく、建築基準法の改正により、リフォーム計画に大きな影響が出る可能性があります。
とはいえ、どんな影響があるのか詳しく理解できている方は少数です。
この記事では、建築基準法改正の内容や、法改正がもたらす2025年以降のリフォーム工事への影響、そして賢いリフォームの進め方について徹底解説します。
近くリフォームを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1.リフォームできない・しにくい物件が増える?

2025年4月の建築基準法が改正以降は、リフォームできない物件やリフォームしにくい物件が増えるといわれています。
具体的には、建築基準法の改正でリフォームにどのような影響があるのでしょうか。
法改正のポイントや、リフォームに与える影響などについて確認していきましょう。
建築基準法改正のポイント
2025年4月から建築基準法の改正により、これまで建築確認申請が必要なかった規模「4号建築物」のリフォームにおいても、確認申請が義務付けられることになります。
4号建築物とは、次のような建築物を指します。
- 木造2階建てまたは平屋で、延ベ床面積が500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下
- 木造以外の平屋で、延べ床面積が200㎡以下
法改正に伴い、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物」が設けられます。
新2号については確認申請の対象となり、新3号建築物は都市計画区域などで確認申請が必要となります。
- 新2号建築物:木造2階建てまたは木造平屋(延べ床面積200㎡超)
- 新3号建築物:木造平屋(延べ床面積200㎡以下)
なぜ2025年が注目されているのか
法改正が施行されると、一般的な住宅が該当する4号建築物の特例は実質的には廃止・縮小されるため、小規模リフォームでも建築確認申請の手続きを行うケースが増えることが予想されます。
そもそも、4号建築物の特例を縮小するのは、国が住宅の省エネ基準適合義務化を促進する目的があります。
小規模リフォームにおいても確認申請の手続きを行うことで、しっかりと省エネ基準に適合したリフォームが実施され安心・安全な住環境の確保につながることが期待できるとされています。
リフォーム費用に影響する具体的な改正点
今回の改正によってリフォーム費用にどのように影響するのか、具体的なポイントとして挙げられるのは、木造2階建て、一定規模の平屋建てにおいてのリフォームで建築確認申請の手続きが必要になると考えられることです。
申請手数料や図面作成など事務手続きの費用が追加されることや、省エネや耐震などの基準に該当する仕様にするための建築費用などが増える可能性があります。
2025年問題をチャンスに変えるために
リフォームを検討している場合、法改正後のリフォーム着手においては費用が追加になる可能性があります。
そのため、費用を抑えるためには、早めにリフォームを行うことがおすすめです。
とはいえ、あわてて必要のないリフォームや無理のあるリフォーム計画を進めるのでは本末転倒です。
この機会に、経験豊富で知識のある専門家を見つけて十分に計画を立て、納得できるリフォームを行いましょう。
2.建築基準法改正でリフォーム費用がアップする理由

確認申請が必要になる建築物に該当するリフォームの場合、費用がアップする具体的なポイントは次の4点です。
断熱性能の基準強化
断熱性能など、省エネ関連の基準に適したリフォームであることが求められます。
そのため、一定基準以上の仕様とするための費用がかかります。
住宅耐震基準の変更
一定の耐震性が必要とされるため、今の法基準に適した構造・仕様にしなければなりません。
間取り変更などの際にも、十分な耐震基準をクリアすることが必要です。
新たに必要となる申請手続きの費用
建築確認申請の手続きには、申請書・図面などの書類作成が必要です。
また申請手数料も負担する必要があります。
工期の延長
一定の省エネ基準、耐震基準に適応する建築物となるため、これまでのリフォーム工事より工期が延長になる可能性があります。
足場や囲いなどの仮設経費や、仮住まい費用なども増えることが想定されます。
3.賢くリフォーム費用を抑えるために知っておきたいポイント
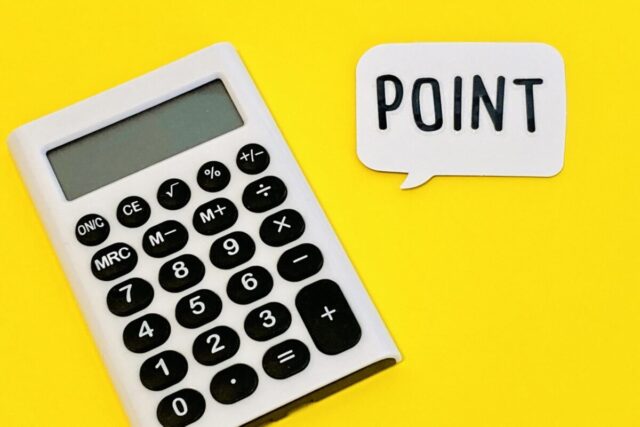
リフォーム計画をしている方の中には、着工が法改正後のタイミングになる可能性がある人もいるでしょう。
2025年4月以降のリフォームであっても費用を抑えるためのポイントをご紹介します。
減築などでコンパクトに暮らすリフォーム
減築を含め、コンパクトに暮らす方向性のリフォームも検討してみましょう。
法改正後では、木造平屋建ての場合なら延べ床面積200㎡以下であれば審査省略の対象とされています。
少ない家族数で暮らしている場合、元のままの床面積をそのままリフォームして費用をかけるよりも、必要な床面積に見直すことで省エネ・耐震性を確保しながらリフォームすることが可能です。
改正後の申請に詳しい業者に依頼する
建築確認申請は、リフォームをする建築主でも申請することは可能とはされていますが、専門的な内容の記載もある申請書であることや図面添付などもあるため業者に依頼するのがおすすめです。
特に法改正後の申請にも詳しい業者が安心です。
早めのリフォーム計画がカギ
リフォーム内容が大枠で決まっているなら、法改正前の2025年3月までにリフォーム工事を着工するのもよいでしょう。
確認申請費用なども抑えられることや、一定基準へのしばりも少なくなります。
補助金や助成金の活用
補助金や助成金を活用することで、リフォーム費用の負担を抑えることができます。
一定の要件に該当すれば、大規模・小規模リフォームでも補助金が使えます。
国、地方自治体とそれぞれに施行されていますので、リフォーム業者に相談してみましょう。
4.2025年以降も使える補助金制度の予測

ここからは、2025年以降も継続されると予測される補助金制度についてご紹介していきます。
国の省エネ促進キャンペーン
2050年カーボンニュートラル実現のために、住宅の省エネ化を促進する補助金制度です。
省エネに関する設備機器または断熱や窓改修などで、一定の要件に該当することで費用の一部を負担するものです。
申請ハードルはそれほど高くないものですので、ぜひ活用したい制度です。
2024年11月29日に、2025年の補助金について発表がありました。
今後も情報が更新されていきますので、各補助事業の最新情報を確認しましょう。
| 事業名称 | 補助額上限 |
| 先進的窓リノベ2025事業 | 最大200万円/戸 |
| 給湯器省エネ2025事業 | 最大20万円/台 |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 最大60万円/戸 |
| 賃貸集合給湯器省エネ2025事業 | 最大7万円/台 |
地方自治体の助成金
福島県では2024年に、県内に所在する既存住宅の省エネ改修、耐震改修等にかかる費用の一部を補助する制度を行っています。
2025年度に継続されるかは未発表ですが、2025年1月から3月頃までは情報収集しながら検討するとよいでしょう。
| 事業名称 | 補助額上限 |
| 福島県省エネルギー住宅改修補助事業(2024年) | 最大96.6万円/戸 |
| 福島県木造住宅用耐震化支援事業(2024年) | 最大120万円/戸 |
5.リフォーム業者の賢い選び方

費用を抑えつつリフォームを進めるには、業者選びがポイントになります。
どのような業者を選ぶべきかご紹介します。
制度や補助金に詳しい業者を選ぶ
一定規模のリフォームは、建設業許可がないと施工できません。
単にリフォーム実績がある会社ではなく、建設業の事業登録がある会社を選びましょう。
また、ホームページで補助金などの案内をしていることや、記事の更新を頻繁に行っていること、お客様に有益な情報を提供している会社は、さまざまなリフォームにも対応できることが期待されます。
地元で長く続く、信頼性の高い業者を選ぶ
地域の風土や特徴を知り尽くしている地元の会社がおすすめです。
地元密着で長く経営している会社なら、信頼性も高いことが多いでしょう。
リフォーム事例が豊富な業者を選ぶ
リフォーム事例が豊富な会社を選びましょう。
リフォーム工事は新築と異なり、途中で予測がつかなかった事態も起きることがあります。
このようなときでも、代案などをしっかりと提案できる会社であることが求められるでしょう。
6.よくある質問(FAQ)

Q1.建築基準法改正の対象はどんな住宅?
建築基準法改正は新築住宅だけでなく、既存住宅を対象としたリフォームにも適用されます。
特に断熱性能や耐震性能が不足している住宅は、改正後の基準を満たすためのリフォームが必要になる場合があります。
Q2.断熱性能の基準強化にどのくらいのコストがかかる?
断熱性能の強化にかかる費用は、住宅の規模や現状の状態によって異なります。
たとえば、窓の交換では1カ所あたり数万円から20万円程度、高性能断熱材の追加工事では1部屋あたり20万円から50万円程度が目安です。
補助金を活用することで、費用の一部を賄える可能性があります。
Q3.耐震補強が必須になる条件は?
耐震補強が必要になる条件は、建築時期や構造によります。
特に1981年の耐震基準改正以前に建築された住宅(旧耐震基準住宅)は、耐震性が不足している可能性が高いため、耐震診断や補強工事が推奨されます。
Q4.補助金の申請スケジュールは?
補助金の申請スケジュールは制度によって異なります。
2024年度の「住宅省エネ2024キャンペーン」は年内申請が必要で、2025年以降の補助金(例:給湯省エネ2025事業)は詳細が発表され次第スケジュールが公開されます。
早めに確認して計画を立てることが重要です。
Q5.建築基準法改正後のリフォームはどのくらい期間がかかりますか?
工事内容によりますが、建築基準法改正に対応したリフォームは通常のリフォームよりも計画や手続きに時間がかかる場合があります。
具体的には断熱改修で1週間から1カ月程度、耐震補強工事で2カ月以上かかることもあります。
事前準備を早めに進めることが大切です。
7.まとめ
今回は、2025年に法改正される建築基準の概要や、リフォーム工事に与える影響、なぜ費用が増える可能性があるのかなどについて詳しくご紹介しました。
改正後のリフォームにもスムーズに対応できるように、リフォーム実績が豊富で信頼できる業者に相談することや、補助金を活用しながら賢いリフォームが進められるように取り組みましょう。












